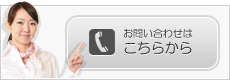ふたつの成年後見制度
備えておくか、おかないか。

この制度は、判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、生活を支援する目的を持つもので、認知症・統合失調症・知的障がいなどによる精神上の障がいにより判断能力が不十分な人たちの財産管理・身上看護を目的とするものです。
成年後見は大別して2種類に分けられ、すでに判断能力の低下がすすんでしまっている方を対象とした「法定後見」と、将来のもしもに備えて自らの財産管理・身上看護を自らが選んだ人に託す契約を結ぶことで行う「任意後見」があります。
あんしんの備え「任意後見」
自分で決める、これからのこと。

本人の判断能力の低下が始まったときに、申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。
任意後見契約においては、本人が任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)に対し、将来、自分に代わって行なってほしい支援内容を、代理権目録という形で決め、その契約内容および任意後見受任者について、公証役場から後見登記がなされます。
その後、本人の判断能力が不十分な状況になったとき、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します。
任意後見監督人が選任されることで、裁判所が任意後見人が本人のために正しく仕事を行なうか、間接的にチェックすることになります。
法定後見との大きな違いは、後見人もその仕事内容も、全てあらかじめ自分で決めておけると言うことです。この違いが、実は大変大きな違いであり、任意後見をお勧めする理由なのです。
備えがなければ「法定後見」
最後のセーフティーネット

援助者に対し同意権(取消権)または代理権、あるいはその両方を付与することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
法定後見では本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。
法定後見開始の申し立ては、被後見人となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行います。申し立ての際には、申立書のほか、本人の戸籍謄本、診断書などいくつかの書類を添えなければなりません。申し立ての費用は、概ね10,000円以内になりますが、鑑定が必要な場合は鑑定料が50,000円~100,000円程度必要となります。
申し立ての際に、成年後見人として適当な人がいればその人を候補者を推薦できます。適当な候補者がいない場合は、家庭裁判所がどの親族とも利害関係のない、専門家等の第三者を成年後見人に選任することになりますが、審判まではやや時間がかかることになります。
もうひとつの備え「逝後事務委任」
誰にも迷惑をかけない終わり方

委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して短期的な逝後の事務を委任することができます。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定したいという方もいますが、法定遺言事項にはあたらず、附言事項となるので、実効は定かではありません。
ですので、葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人との打合せや準備をしておくことが重要です。